




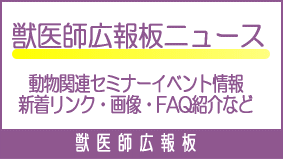
 |
 |
 |
 |

|
意見交換掲示板過去発言No.0000-199908-326
| レントゲン線の被爆について |
| 投稿日 1999年8月28日(土)14時08分 プロキオン
他の会議室で話題にあがったことですが。 少し長いので、結論からいうと心配されているような危険な被 爆量はまずありません。 まず、放射線については1つ国だけではなく、各国がその取り 扱いこうしようという取り決めを「条約」で行います。 これを受けて国内法を整備します。これが「原子力基本法」で あり、さらにその下に「放射線安全法」があります。 これらの中で規定されている放射線には、実のところ動物病院 におけるX線は該当しません。それは実効エネルギー線量がは るかに小さいためです。 世の中には「自然放射線」というものが存在し、何もしない状 態で我々が浴びている天然の放射線があるのです。宇宙線・大 地・空気などから浴びています。その線量は1年間で約2.4 ミ リシーベルトになります。そしてこの線量というのは、通常の 胸部X線撮影の25〜40回分に相当します。人は何もしてい なくても年に25〜40回のX線撮影を受けているのと同じ量 の放射線をあびているのです。 富士山の頂上や高空を飛ぶ航空機関係では、倍近い値になりま す。 犬や猫のX線撮影には、よほど大型犬でも無い限り、人体を上 回る線量は使用されません。獣医医療法で規定されている「管 理区域」の設定を必要とする線量も1週間に400〜500回 の撮影をして初めてその照射野が該当してきます。保定者がい る場所は該当しません。 どうしてこのような大きな数値が設定されているかというと、 獣医療法を制定する際に人間の医療法をそのまま参考としたた めですね。医療法では放射線の線量以外に放射性同意元素の存 在を含めて設定したのに、こちら(放射性同意元素)を落とし てしまっているからです。 実際の運用上は、フイルムバッチや簡易なポケット線量計でX 線の線量を測定しておくことになっていますが、これもまず被 爆が検出されることはありません。検出されるようでしたら、 X線の照射器か保定に問題があって1次X線を浴びてしまった 可能性があります。 本質的には「実効線量当量」と言って、体の4ケ所の線量を測 定し、これに「組織吸収計数」を乗じた数値をもって被爆線量 のモニタリングとすることになっています。 ただし、これを実行されている方はまずいないのではないでし ょうか? 普通は「胸部」や「腹部」の数値をもって代表値に しているはずです。実効線量当量をだすのには計算値しかない のです。 何故このようなことが許されるかというと医療法の第30条の 18に週30ミリレントゲン以下なら被爆線量を測定せずに計 算だけで良いという項目があるのです。 そのくらい、X線作業に従事する者の被爆線量は低レベルで検 出しにくいのです。 早い話がX線でお湯はわかせんませんが、同じ電磁波である電 子レンジでは可能です。(エネルギーの使い方が異なりますが) さらに、携帯電話の着信時には電子レンジのおよそ300倍く らいの電磁波が発生します。 とはいっても、余分な線量を浴びる必要はさらさらありません ので、注意はするのにこしたことはありあせん。実際に被爆を モニタリングしたいのなら、リングバッチの方が適しているか もしれません。これらの測定具の積算値から自然放射線を差し 引いた値があなたの被爆量になります。 女性の場合、獣医療法では妊娠から出産まで10ミリシーベル トのX線を浴びても良いことになっていますが、「労働安全衛 生法」では認められていません。不安がある場合はこちらの法 律に従ったほうが良いでしょう。 では、獣医療法が労働安全衛生法に違反しているのではないか という疑問が出てくると思いますが、この辺は難しいところで す。先にも述べましたが、医療機関で扱うX線が法律上の放射 線に該当する程のエネルギーを有していないので、法律の上で は放射線として扱ってもらえない可能性があるからです。 余分な被爆はしない、けれどもいたずらに恐がる程危険な線量 は出ていないというところが話のおとしどころです。 |
|
|
獣医師広報板は、町の犬猫病院の獣医師(主宰者)が「獣医師に広報する」「獣医師が広報する」 ことを主たる目的として1997年に開設したウェブサイトです。(履歴) サポーターや広告主の方々から資金応援を受け(決算報告)、趣旨に賛同する人たちがボランティア スタッフとなって運営に参加し(スタッフ名簿)、動物に関わる皆さんに利用され(ページビュー統計)、 多くの人々に支えられています。 獣医師広報板へのリンク・サポーター募集・ボランティアスタッフ募集・プライバシーポリシー 獣医師広報板の最新更新情報をTwitterでお知らせしております。 @mukumuku_vetsさんをフォロー
Copyright(C) 1997-2026 獣医師広報板(R) ALL Rights Reserved |