




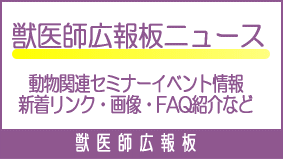
 |
 |
 |
 |
 |
意見交換掲示板過去発言No.0000-200701-67
| 人間は何故鳥インフルエンザに罹りにくいのか、 |
|
投稿日 2007年1月14日(日)13時57分 投稿者 プロキオン
また、宮崎県で新たな発生があったようなので、不安払拭のために書きます。 今分かっていることを簡単に言ってしまうと、インフルエンザウイルスが細胞に侵入する際に利用するレセプターの分布が人間と鳥では違っているから、鳥では広く分布していて利用できるレセプターが、人間にはあまり分布していないからということになります。 インフルエンザウイルスは、その遺伝子DNAを構成の相違から、A・B・Cと大別されており、鳥インフルエンザは、A型に属します。 このA型もウイルスも、粒子の表面の赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の活性との組み合わせによって、さらに細分されています。この中のH5型とH7型が、所謂「高病原性」と呼ばれる「強毒株ウイルス」ということになります。 なぜかというと、このタイプのものだけが、ウイルス内にある種の情報を持ち、蛋白分解酵素を利用して感染者(鳥の)の体内の全身で増殖することが可能だからです。ウイルスが増殖できる部位が広く多いので増殖スピードが他のタイプのウイルスよりも速く、病勢として重篤になりやすいという結果に繋がるのです。 したがって、この能力を持たない鳥インフルエンザウイルスは、同じ鳥インフルエンザウイルスであっても感染しても病勢が弱く、「低病原性」と呼ばれることになります。低病原性の鳥インフルエンザウイルスでは、全身性ではなく、限られた増殖部位でしか増えることはないということなのです。 ウイルス側の要因としても、普通は増殖に適した部位(組織による細胞の差)が存在するということになります。 また、宿主側にもウイルスの感受性を左右する要因があります。これが先ほど述べた「レセプター」です。ウイルスが細胞内に侵入するときのとっかかりともいう足場です。 これがどこにどのくらい分布しているかで、感染しやすいかが左右されます。 このレセプターの分布が人間では気管支粘膜上皮や肺の一部であって、鳥類のように消化器までに広く分布しているわけではないのです。 レセプターが少ないということは、それだけ感染しにくいということになります。鳥に感染が成立するウイルスの量よりもさらに多くのウイルス量を必要とするということになりますし、また、それだけ長くウイルスにさらされている時間を必要とするということなのです。 それが人間が鳥インフルエンザウイルスに罹りにくい理由なのです。 そして同時に、これが鶏に対してワクチンが摘要されない理由なのです。ワクチンは、その対象疾病が根絶できない、病原体といつ接触してもおかしくないという環境でこそ有効なのです。それは、病原体に感染する可能性があるからこそということであって、鳥インフルエンザで言えば、我が国に広く定着してしまった場合ということになります。一度に大量のウイルスにさらされなくても、少しずつでも長時間に亘ってさらされるという可能性を残すことになるからです。 人間社会にまで及ぼす影響を考えると、鶏の摘発と淘汰処分こそが、最も確実で後世に対する被害も少ない選択ということになります。 一口に「高病原性ウイルス」と言っても、鳥によって病勢に差があります。水鳥たちがウイルスの運び屋ではないかと話題になります。これも感染性・増殖性に鳥の種類による差があると受け取られているからです。 つまり、渡り鳥である水鳥達は、やはり抵抗性があるのではないかということですね。だから発病せずに日本に渡ってくるのではないかと疑われているわけです。 でも、私はむしろ、水鳥とインフルエンザウイルスとの関係こそが普通であって、逆に養鶏の形態こそが、感受性に富む鶏達を一箇所に大量に集めすぎているのだと考えています。 それが養鶏業の姿ですから、いけないとは考えません。特殊な条件化に感受性のあるものを集めているだけのことですから、養鶏業の方達こそが真剣にとりくんでいただければ、一般の方がテレビの報道で危機感を募らせる必要はないですし、神経質になることはないと思います。
|
|
|
獣医師広報板は、町の犬猫病院の獣医師(主宰者)が「獣医師に広報する」「獣医師が広報する」 ことを主たる目的として1997年に開設したウェブサイトです。(履歴) サポーターや広告主の方々から資金応援を受け(決算報告)、趣旨に賛同する人たちがボランティア スタッフとなって運営に参加し(スタッフ名簿)、動物に関わる皆さんに利用され(ページビュー統計)、 多くの人々に支えられています。 獣医師広報板へのリンク・サポーター募集・ボランティアスタッフ募集・プライバシーポリシー 獣医師広報板の最新更新情報をTwitterでお知らせしております。 @mukumuku_vetsさんをフォロー
Copyright(C) 1997-2026 獣医師広報板(R) ALL Rights Reserved |